合同会社 Hokkaido Design Code

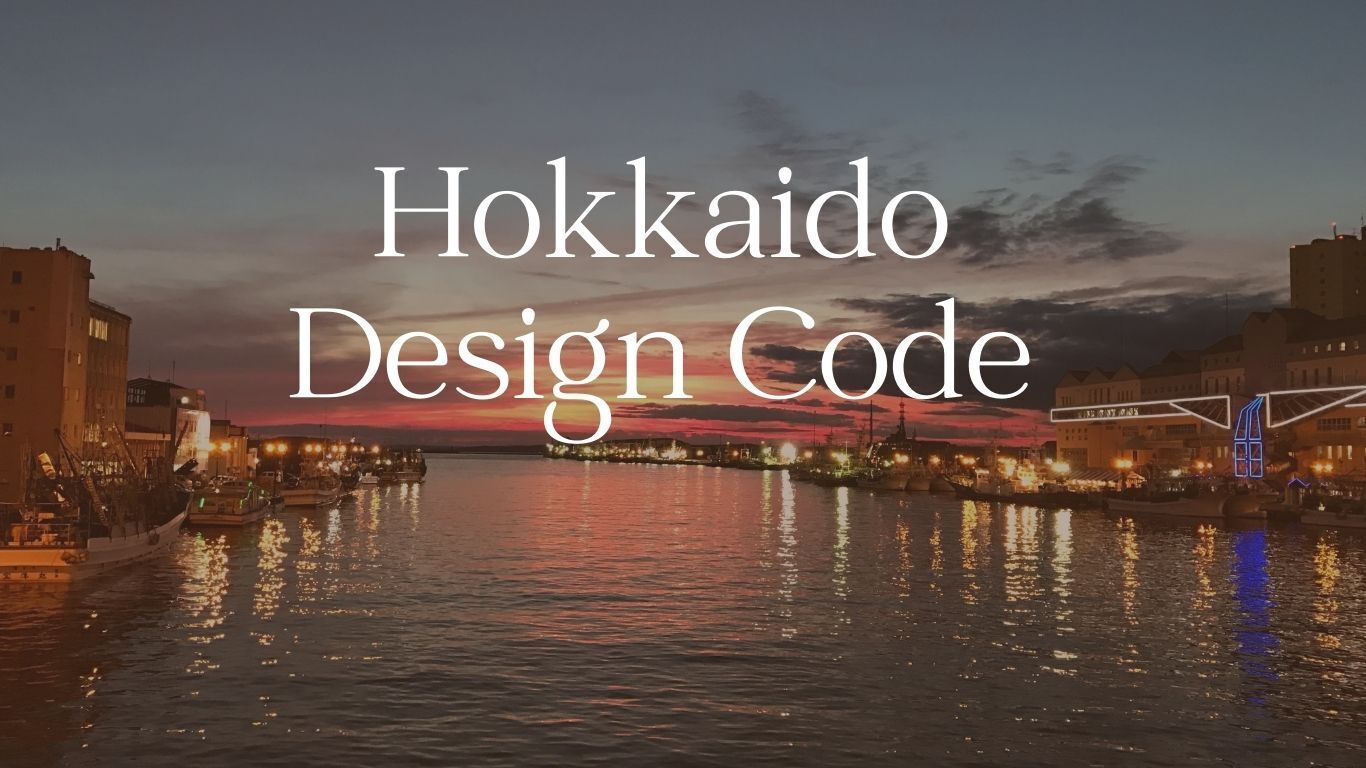
業種
情報通信業
企業規模
~10名
課題
採⽤と定着 / 地域活性化 / エンゲージメント向上
合同会社Hokkaido Design Codeは、メディア運営の経験を活かし、地域のPRやイベント企画を通じて地域とのつながりを維持してきました。コロナ禍においても、コミュニティスペースの運営やDXコンサルティングにより地域課題の解決に貢献。東京と遜色ない高単価な仕事を地元で創出し、地域経済の活性化と多様な人材の雇用を目指しています。
■YouTube動画
<挑戦>
合同会社Hokkaido Design Codeが、テレワーク推進と多様な人材の活躍という目標に向き合う中で直面した課題は、特徴的でした。
■副業メンバーとのコミットメント
初期の会社設立メンバーには当初、副業が難しいメンバーもいたため、柔軟な働き方が可能なメンバーを中心に会社を立ち上げました。しかし、現在も多くのメンバーが副業として参加しているため、デザインコードの仕事にフルコミットできないことを苦慮してしまう点が課題でした。代表はフルコミットする必要は無いという意思を伝えても、メンバー側が寄与できているのか、どうすればできるのか考えこんでしまっていました。
■地域における雇用の創出と単価向上
釧路では働く場所が少ないと感じる人が多く、地元の企業が地元の人を雇用する仕組みが不足していました。また、IT・クラウド系の仕事は東京の会社に流れ、地元での高単価な仕事が少ないという現状がありました。
<独自戦略>
これらの課題を乗り越えるため、合同会社Hokkaido Design Codeは、テレワークを最大限に活用し、社員一人ひとりに寄り添う独自の戦略を実行しました。
 ■柔軟な働き方の受容:
■柔軟な働き方の受容:
メンバーが副業でコミットできないという課題に対し、「できる時にできることをやってもらう」というスタンスを一人一人と、オフラインも含めてしっかりコミュニケーションを行い、柔軟に対応しています。
釧路の観光施設内にコミュニティスペースを立ち上げ、地域住民が利用しやすい場所を提供。これにより、地域の人々と観光客の交流を促進し、地域とのつながりを強化しています。
■ITと地域貢献の「両輪」経営:
システム開発やDXコンサルティングを主軸に収益を確保しつつ、地域のPRやイベント企画を通じて地域課題の解決に貢献しています。特に、サイボウズのパートナー企業として認定されたことで、IT企業としての信頼性と認知度を高めています。
■山本かおり氏のフルコミット:
経験豊富な山本かおり氏が広報や事務の経験を活かし、フルコミットで業務をサポート。これにより、チーム内の連携が強化され、業務効率の向上が図られています。
■高単価案件の地域内還元:
東京の会社に依存せず、地元で高単価の仕事を受注し、地元の人々に還元する仕組み作りを目指しています。
<成果>
これらの取り組みの結果、合同会社Hokkaido Design Codeは生産性向上、従業員エンゲージメントの強化、そして高い定着率という目覚ましい成果を上げています。
■地域との強固なつながり
コロナ禍においても地域のイベントやPR活動を継続し、地域とのつながりを維持しています。コミュニティスペースの運営を通じて、地域住民が気軽に集える場を提供し、地域の活性化に貢献しています。
■多様な働き方の実現とメンバーの自律性向上
北海道、東京、長崎にメンバーが点在し、それぞれが異なるバックグラウンドを持ちながら、場所にとらわれずに活動しています。メンバーが自ら企画を提案し、収益化を目指すことで、モチベーションの向上にもつながっています。
■地域の認知度向上と雇用創出への貢献
サイボウズのパートナー企業として認定されたことで、地域のIT企業としての認知度が向上。地元企業と協力し、地域の人々を雇用する仕組み作りを積極的に進めています。
<こだわり>
合同会社Hokkaido Design Codeが特に重視し、社員が輝く職場を築き上げるために工夫を凝らした点は、以下の通りです。
 ■「人」を重視する採用と信頼関係
■「人」を重視する採用と信頼関係
山本かおり氏は、「仕事内容等よりも誰とやるかを優先」し、琴絵氏と共に働くことを選んだと述べています。琴絵氏の「想像してないことがふっと湧いてくる」面白さや、様々な経験ができる環境が魅力となっているそうです。
■挑戦を後押しする企業文化
琴絵氏やメンバーの考え方が基本となり、新しい企画やイベントに自由に挑戦できる文化があります。これにより、多様なアイデアが生まれ、地域の活性化につながっています。
■経営者としての責任と地域への還元
琴絵氏は「会社の売り上げは地域に還元するもの」と考えており、地元の雇用創出や高単価な仕事の提供を通じて、地域に貢献することを使命としています。
<苦労>
テレワーク導入と定着の道のりで、合同会社Hokkaido Design Codeが経験した苦労と、それを乗り越えるための努力をご紹介します。
■副業メンバーのコミットメント維持
メンバーが副業であるため、デザインコードの仕事に全てをコミットできないことにジレンマを感じた時期がありました。メンバーからは「役に立ってないのではないか」「辞めた方がいいのではないか」といった相談も受けたといいます。
■乗り越えるための「できる時にできることを」というスタンス
この課題に対し、琴絵氏は「できる時にやれることをやってもらえればいい」というスタンスでメンバーを説得し、支えてきました。家族の事情など様々なフェーズがある中で、柔軟に対応することで、メンバーの離脱を防ぎ、共に活動を続けています。
■コミュニケーションツールの活用と定例会の導入
以前はFacebookメッセンジャーでのやり取りが中心で、メンバーの状況が見えにくい時期もありました。しかし、案件が増えるにつれて、チャットツールやkintoneを導入し、案件管理やタスク管理を強化。山本かおり氏の参加により定例会も設けられ、情報共有と連携がスムーズになりました。
<未来>
合同会社Hokkaido Design Codeは、これからも働き方の進化を追求し、社員と共に目指す未来像を描いています。
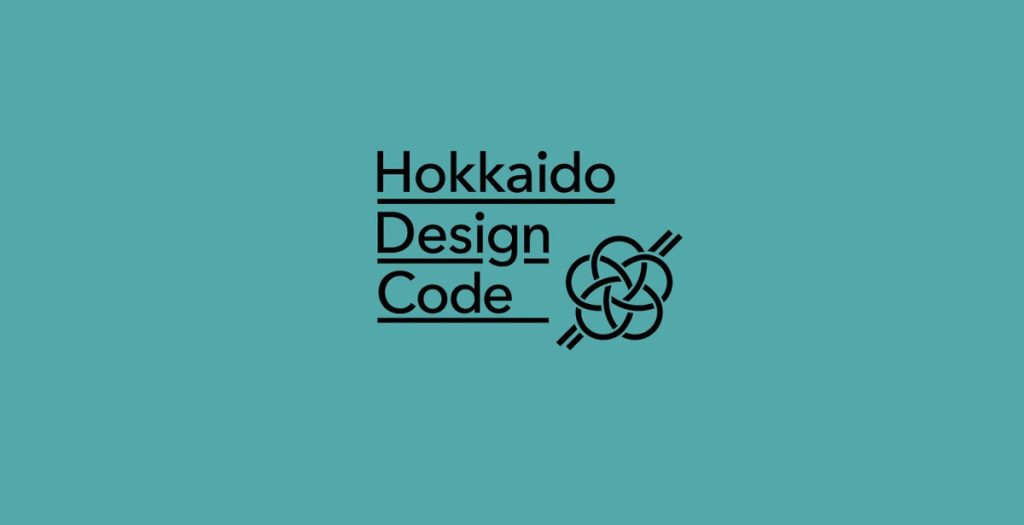
■地域雇用創出の仕組みづくり
地元企業と協力し、地域の人々を雇用するための仕事を生み出すことを目指しています。特に、東京の会社に依存せず、地元で高単価な仕事を提供できる仕組みを構築したいと考えています。
■関係人口の増加とITの活用
イベントを通じて県外から人を呼び込み、関係人口を増やす取り組みを継続していきます。また、IT、特にkintoneを活用したシステム開発やDXコンサルティングを軸に、地域のDX推進を支援し、地域全体の生産性向上に貢献します。
■「北海道スタイル」の確立と全国への展開
「Hokkaido Design Code」という社名には、北海道のデザインがドレスコードのように、みんなが繋がり、北海道スタイルがスタンダードになるようにという思いが込められています。
将来的には、この北海道で確立したモデルを他の地域でも展開し、地域を活性化できる、地域に経済的価値をもたらす企業を全国に増やしていきたいと考えています。
<Advice>
合同会社Hokkaido Design Codeから、より良い働き方を模索するすべての企業へのアドバイスです。
■「人」を大切にする経営:
メンバーがそれぞれの事情を抱えながらも、できる時に最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、柔軟な姿勢でサポートすることが重要です。個々のライフフェーズに合わせた働き方を許容することで、エンゲージメントの高いチームを築くことができます
■地域課題への積極的な関与:
地域に根差した企業として、地域の課題解決に貢献する意識を持つことが、事業の成長にもつながります。地元の企業や行政と連携し、雇用創出や高単価な仕事の機会を創出していくことが、持続可能な地域社会の実現に不可欠です。
■ITとテレワークの積極的な活用:
ITツールやテレワークを積極的に活用することで、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を実現し、多様な人材の確保と生産性向上を図ることができます。
■こちらもオススメ!
・岡崎市テレワーク就労支援事業 ・独自の制度でコミュニケーションを革新。テレワークで生産性とエンゲージメントを向上! ・中小企業21万社に「働き方改革」を実現する「スクラムパッケージ」を提供し、8万社に「テレワーク環境」を提供 ・ワークスタイルの変革により、ワークインライフの実現へ! ・観光地「富良野」でワーケーション受入による関係人口創出・拡大への挑戦 ~観光客とは異なる新たな誘客を目指して~ ・建設業におけるテレワーク成功の秘密こうすればテレワークは経営戦略として生きることが実証された 〜18年間で培ったテレワークの実践知から学ぶ〜・『働き方DX事例集 ~変革への挑戦~』はコチラ











