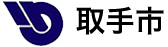職員負担50%減!取手市は「生成AI副操縦士」とどう働き方を変えたのか?
議会答弁の作成に膨大な時間を費やしていませんか?あるいは、多様な住民一人ひとりとのコミュニケーションに課題を感じていませんか?
茨城県取手市は、生成AIや音声認識といった先進技術を「職員の頼れる相棒」と位置づけることで、これらの課題に正面から向き合い、働きがいと住民サービスの質の向上を同時に向上させる「働き方DX」を成功させました。その軌跡を追います。
導入団体情報
|
団体名: 茨城県取手市 |
導入前の課題(ビフォー):「時間との戦い」と「コミュニケーションの壁」
取手市役所では、主に2つの大きな課題に直面していました。
|
【膨大な議会答弁作成の負荷】 議会対応は自治体職員の重要な業務ですが、答弁書の作成には膨大な時間と労力がかかっていました。過去の膨大な議事録から関連答弁を探し出したり、各種計画との整合性など正確かつ分かりやすい文章を作成する作業は、職員にとって大きな負担となり、長時間労働の一因となっていました。
|
|
【多様な住民とのコミュニケーションの障壁】 市役所の窓口には、日々様々な市民が訪れます。特に、聴覚に障害のある方とのコミュニケーションには課題がありました。手話通訳者の配置は週1日に限られています。 また、聴覚に障害があっても手話を使用しない方に対しては、筆談での対応が中心でしたが、多くの時間と労力を要し、特にお互いの複雑な説明内容が正確に伝わっているか、双方に不安が残る状況でした。コロナ禍で窓口に設置されたアクリル板は、さらにコミュニケーションを難しくしていました。
|
取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):AIは"副操縦士"、最適な対話を支援
取手市は、これらの課題解決のため、職員の業務を「支援」し、人にしかできない「対話」の時間を創出することに主眼を置いた2つのDX施策を導入しました。この取り組みは、議会でのAI文字起こし(議事録作成支援)の活用経験から発展したものです。
1.生成AIを用いた議会答弁書作成支援システム
生成AI(ChatGPT)を活用し、答弁書作成を支援するシステムを全国に先駆けて導入しました。職員が質問の骨子を入力するだけで、AIが想定問答の素案を複数パターン作成します。
また、過去の取手市議会の会議録やプレスリリースされた先進・関連事例の検索と要約機能であったり、市の各種計画やデータを読み込ませて素案に反映させるといった機能を、1クリックまたはドラッグ&ドロップで容易に行うことができます。
【過去の議事録検索と要約】
関連する過去の答弁を瞬時に検索・要約し、論理の一貫性を保ちます。
【プロンプト自動生成】
AIに不慣れな職員でも、簡単な操作で最適な指示(プロンプト)をAIに与えられるよう、システムがサポートします。
【多角的な視点の提供】
答弁のニュアンスを変更したり、他の自治体の先進事例を調査したりする機能も搭載。AIをまるで優秀な同僚や先輩のように活用できます。

[生成AI議会答弁書作成支援システム説明会の様子]
2.音声認識文字表示ディスプレイ
障害福祉課の窓口に、リアルタイムで会話を文字に変換して表示する透明なディスプレイを設置しました。職員と来庁者の間に置かれたマイクが音声を拾い、AI音声認識技術が瞬時にテキスト化してディスプレイに映し出します。
【円滑なコミュニケーション】
聴覚に障害のある方も、会話の内容をリアルタイムで目で見て確認できるため、安心して相談できます。
【見えない情報も可視化】
職員が他部署に内線で問い合わせる内容まで文字化されるため、来庁者は「自分の相談が正確に伝わっている」という安心感を得られます。
【手話通訳不在時をカバー】
週1回の配置だった手話通訳者に頼らずとも、円滑な意思疎通が可能になりました。

[取手市窓口での活用]
期待される成果・効果 (アフター):創出された時間と、深化した対話
これらのDX施策は、目覚ましい成果を上げています。
定量的成果
定性的成果
【職員の働きがい向上】
答弁作成の負担が減ったことで、職員はより創造的で付加価値の高い業務に時間を割けるようになりました。岩﨑弘宜情報管理課長は「AIは職員の"副操縦士"、時には上司や同僚の役割も果たしてくれる」と語ります。
【住民サービスの質向上】
聴覚障害のある方からは「スムーズに伝わるようになった」「書かずに相手に内容が伝わるため楽になった」との声が寄せられています。
【新しい行政課題への迅速な対応】
例えば「インクルーシブ教育」といった新しいテーマの質問に対しても、AIが多角的な視点を提供してくれるため、迅速かつ質の高い答弁作成が可能になりました。
成功のポイント・工夫した点:人に寄り添うテクノロジー活用
取手市の成功の裏には、テクノロジーを主役にするのではなく、あくまで「人」を支援するためのツールとして捉える、徹底した利用者目線がありました。
【職員に寄り添うシステム設計】
議会答弁書作成支援システムでは、AIに不慣れな職員でも直感的に使えるよう、プロンプトを自動生成する機能を設けるなど、使いやすさを追求しました。
【現場の声を反映した改善】
音声認識ディスプレイでは、集音マイクの指向性を来庁者側と職員側で変えたり、文字を見やすくするために白黒反転表示させたりと、現場での試行錯誤を重ねて改善を加えています。
【「AIは副操縦士」という明確な位置づけ】
AIに100%依存するのではなく、あくまで職員の能力を拡張する「副操縦士」と位置づけたことが、職員の心理的な抵抗を減らし、積極的な活用を促しました。
今後の課題、取り組み
取手市の挑戦はまだ続きます。今後は、議会答弁書作成支援システムを議員自身が調査・研究のために活用することで、より質の高い政策議論へとつなげていくことが期待されています。 そのための議員向け説明会も既に開催済みです。また、音声認識ディスプレイは、外国人対応時の翻訳ツールとしての活用も検討されています。
あなたの組織では、AIやデジタル技術をどのように"頼れる相棒"として活用できるでしょうか?日常業務に潜む課題を、新しいテクノロジーで解決するヒントがこの事例には隠されています。
関連情報・ナビゲーション
お問い合わせ
日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)