「何をするんだ!」猛反発から「社長、これ便利です」へ。明北電気工業が挑んだ、建設業の“常識を変える”働き方DX
導入企業情報
|
[岩垂巧磨社長]
|
|
|
|
|
|
導入前の課題(ビフォー):このままでは未来がない」コロナ禍と2024年問題が突き付けた現実
有限会社明北電気工業を率いる代表取締役 岩垂 巧磨(いわだれ たくま)氏は、数年前、強い危機感を抱いていました。
【コロナ禍と顧客からの要請】
パンデミックにより、非対面・非接触が求められる社会へ。主要顧客である大規模工場からは、BCP(事業継続計画)対策として、従業員の行動履歴管理など、厳格な感染対策を求められていました。
【タイムカードのための出社】
現場作業を終えた社員が、タイムカードを押すためだけに一度会社へ戻る。この毎日の移動時間が、大きな無駄となっていました。
【目前に迫る「建設業の2024年問題」】
時間外労働の上限規制が目前に迫る中、「働く時間を減らし、給料を上げ、従業員を満足させる」という、従来のやり方では達成困難な課題に直面していました。
【見えない業務への不安】
直行直帰を導入したくても、現場での安全管理や業務内容が正確に把握できなくなるのではないか、という懸念が大きな壁となっていました。

取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):「社員が楽になるために」社長自らが作り上げたDXの仕組み
「これはもう、やるしかない」。覚悟を決めた岩垂氏は、社員が会社に立ち寄らずとも全ての業務が完結する、全く新しい働き方の実現に向けて、DXツールの導入を一気に進めました。
1.クラウド勤怠管理で直行直帰を実現
クラウド型の勤怠管理システム(マネーフォワード)を導入。 スマートフォン一つでどこからでも出退勤や休憩の打刻、さらには有給休暇の申請まで可能にし、「直行直帰」の働き方を実現しました。
2.ノーコード活用で業務・安全管理を「見える化」
業務報告や安全管理のツールとしてkintoneを採用。単に導入するだけでなく、電柱に登る前のフルハーネス型墜落制止用器具の始業点検や、毎朝のアルコールチェックといった自社の業務フローに合わせ、社長自らが「社員が誰でも簡単に使える」ようにアプリケーションを設計・構築しました。報告は社長が承認するプロセスとし、離れていても安全への意識を高く保つ仕組みを作り上げました。
3.情報共有とコミュニケーションの円滑化
全社員にiPad miniを貸与し、図面や仕様書の閲覧をペーパーレス化。ZoomやTeamsといったオンライン会議ツールも活用し、顔を合わせる時間が減っても密なコミュニケーションを維持しました。
4.セキュリティ対策
どこからでも安全に社内システムにアクセスできるよう、VPN(仮想プライベートネットワーク)を構築。利便性と安全性を両立させました。
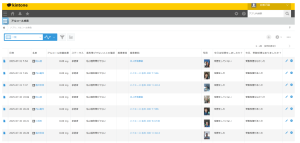 [アルコールチェック画面]
[アルコールチェック画面]
導入後の成果・効果 (アフター):働きやすさが、企業の成長力に変わった
当初、「何をするんだ!」と社員から強い反発があったという今回の改革。しかし、その利便性が浸透するにつれ、会社は大きく変わりました。
定量的成果
【生産性向上と待遇改善の両立】
創出された時間で生産性を高め、長時間労働を削減。にもかかわらず、会社の業績は右肩上がりに成長し、社員の賃金ベースアップも実現しました。
定性的成果
「体がとても楽になった」 「有給が申請しやすくなった」 という声が上がるなど、従業員の働きやすさが大幅に向上。
【安全管理文化の醸成】
社長が毎日チェック・承認する仕組みにより、社員一人ひとりの安全意識が向上。
【「生きたマニュアル」として機能】
kintoneで整備された作業手順は、若手社員の教育ツールとしても効果を発揮しています。
成功のポイント・工夫した点:「二度とやりたくない」ほど苦労したDXの先にあったもの
このDX成功の裏側には、岩垂氏の並々ならぬ情熱と工夫がありました。
【徹底した「社員ファースト」の視点】
「いかに分かりやすいシステムを作るか。そこが一番苦労したところです」と岩垂氏は語ります。 業者任せにせず、自社の業務を知り尽くした社長自らが「社員に寄り添ったシステムづくり」に2年近くの歳月を費やしたことが、社員に受け入れられる最大の要因でした。
【「やらされている感」を払拭する粘り強い対話】
最初は抵抗した社員たちにも、改革の全体像やビジョンを丁寧に説明。実際に使ってみて「便利だ」と実感してもらうことで、反感を納得感へと変えていきました。
【覚悟を持った一気通貫の改革】
勤怠管理だけ、業務報告だけ、といった部分的な導入ではなく、インフラ、セキュリティ、各種アプリケーションまで、必要なものを全て洗い出し、計画的に、そして一気に導入。これにより、真に「場所にとらわれない働き方」を完成させました。
今後の課題、取り組み:より柔軟で、創造的な働き方を目指して
「場所にとらわれない働き方に寄り添うDX」 を成功させた明北電気工業。その目はすでに次を見据えています。
「今後は、家庭の事情などに合わせてより柔軟に働けるフレックスタイム制も導入したい」。 岩垂氏はそう語ります。さらに、人材不足という大きな課題を乗り越えるため、報告書作成などを効率化する「生成AIの活用」 も重要なテーマとして検討を進めています。
この挑戦は、DXが単なる業務効率化のツールではなく、社員の人生に寄り添い、企業の未来を創造するための強力な武器であることを示しています。
あなたの会社では、昔ながらの慣習や「こうあるべきだ」という思い込みが、従業員の働きやすさや会社の成長を妨げる「見えない足かせ」になっていませんか?有限会社明北電気工業の事例は、その足かせを外すヒントに満ちています。
関連情報・ナビゲーション
テレワーク実践事例サイトはこちら
お問い合わせ
日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)














