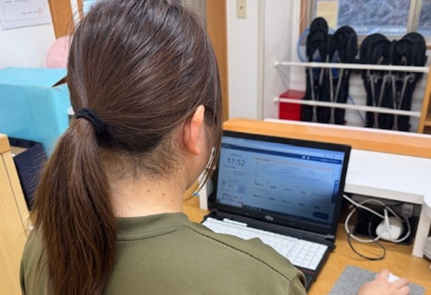「もう、紙と残業に追われない!」
保育の“当たり前”に挑んだキッズ・プランニングのDX戦略。ICTと制度改革で、先生と子どもたちに笑顔の好循環を。
導入企業情報
|
企業名:株式会社キッズ・プランニング(SOUグループ) 業界: 教育・学習支援業(保育)
また、病院内保育所の運営受託や、企業向けの保育コンサルティングも手掛けており、質の高い保育サービスを提供するとともに、地域社会への貢献にも積極的に取り組んでいます。 環境活動やSDGsにも早期から着目し、子どもたちと共に未来を創造する活動を実践しています。 |
|
|
導入前の課題(ビフォー):「なぜ、先生たちはこんなに忙しいのだろう?」現場を覆う課題の数々
「私たち保育の現場は、もしかしたら“当たり前”と思い込んでいる非効率に溢れているのではないか?」そんな問題意識が、株式会社キッズ・プランニングの働き方DXの出発点でした。代表の臼木淑子氏をはじめ、現場の保育士たちは、日々の業務の中で以下のような課題に直面していました。
【手書きだらけの保育書類】
日々の連絡帳や指導計画、保育日誌など、膨大な手書き書類の作成・管理に多くの時間が割かれていました。 書式の不統一や重複記載も多く、保育士の大きな負担となっていました。
【アナログな保護者連絡】
電話や手紙が中心の保護者連絡は、緊急時の情報伝達の遅れや、共働き家庭のライフスタイルとのミスマッチが課題でした。
【会議や研修のための移動時間】
複数施設を運営する中で、会議や研修のたびに発生する移動時間が、保育士の貴重な時間を奪っていました。
【複雑なシフト管理と長時間労働】
保育需要の変動に対応するためのシフト作成は複雑を極め、特に早朝や延長保育の時間帯には人手不足が生じやすく、一部の職員に業務負担が集中し、長時間労働が常態化する懸念がありました。
【採用難と保育の質の維持】
厳しい労働環境は保育士の離職にも繋がりかねず、新たな人材確保も難しい状況でした。結果として、保育の質を維持・向上させていく上での大きな壁となっていました。これらの課題は、保育士が子どもたち一人ひとりと丁寧に向き合う時間を奪い、心身の疲弊にも繋がりかねない、まさに喫緊の経営課題だったのです。
取り組み内容・導入したDX施策 (アクション):「当たり前」を疑う勇気。ICTと制度改革の両輪で、現場に笑顔を!
「このままではいけない。子どもたちの笑顔のために、まずは先生たちが笑顔で働ける環境を作らなければ」。その強い想いから、キッズ・プランニングは、ICTの積極活用と労働環境の抜本的な見直しという、二つの大きな柱を軸とした働き方DXに着手しました。
【ICT活用による徹底的な業務効率化】
|
[ルクミーの活用] |
保育業務支援システム「ルクミー」の導入 これまで手書きだった連絡帳、出欠管理、指導計画などを一元的にデジタル化。 保護者との連絡もアプリ上で完結できるようになり、ペーパーレス化と情報伝達の迅速化を同時に実現しました。 緊急時の個別連絡もスムーズになり、保護者の安心にも繋がっています。 |
ビジネスチャット「チャットワーク」の導入
職員間の情報共有やタスク管理を効率化。 これまで紙や口頭で行っていた連絡事項もチャットで共有することで、申し送りの漏れを防ぎ、必要な情報へ誰もがアクセスしやすい環境を整備。会議のための移動時間削減にも貢献しています。
|
[ICカード打刻] |
勤怠管理システム「保育士バンクコネクト」の導入 ICカードによる打刻システムを導入し、勤怠管理をデジタル化。 これにより、手作業による集計ミスや不正打刻を防ぎ、給与計算業務も大幅に効率化されました。 職員自身もリアルタイムで勤務状況を確認できるようになり、時間管理への意識向上にも繋がっています。 |
ウェブ会議システムの活用
定期的な会議や研修をオンライン化することで、移動時間を大幅に削減。全国の保育士がオンラインで繋がり、学びを共有する機会も創出されました。
【「変形労働時間制」の導入による柔軟な働き方の実現】
|
保育園の開園時間は長く、日々の園児数や行事によって必要な人員数が変動します。従来の固定的なシフトでは、どうしても人員配置に無駄が生じたり、逆に対応が困難になったりする場面がありました。
そこで、2025年6月から「変形労働時間制」を導入。これにより、月単位・年単位で労働時間を調整し、業務の繁閑に合わせた柔軟なシフト作成が可能になります。 ピークタイムには人員を厚く配置し、比較的ゆとりのある時間帯には少人数で対応するなど、メリハリのある人員配置で、保育の質を維持しながら職員の負担軽減を目指しています。
|
[職員みんなで話し合い] |
導入後の成果・効果 (アフター):DXが生んだ「時間」と「心」のゆとり。そして、子どもたちの笑顔へ
これらのDX施策は、着実に成果として現れ始めています。
【保育業務の大幅な効率化】
✔「ルクミーの導入で、書類作成時間が本当に短縮されました。以前は毎日夜遅くまでかかっていた記録作業が、今では子どもたちが降園した後にさっと終えられることもあります」と現場の保育士は語ります。 保育書類の統一化・簡素化により、これまで書類業務に費やしていた時間を、子どもたちと向き合う時間や教材研究、研修といった、より創造的な活動に充てられるようになりました。
✔ 保護者からは、「アプリで園の様子がリアルタイムに分かり、安心して預けられるようになった」「欠席連絡などがスマホで簡単にできるので助かる」といった喜びの声が寄せられています。
【職員の働きがい向上と職場環境の改善】
✔ 勤怠管理の透明化は、職員の時間に対する意識改革を促し、不要な残業の削減に繋がっています。
✔ 変形労働時間制の導入により、「これまでは休みたくても休めなかった行事の後などに、計画的に休暇を取りやすくなった」「自分の時間が増え、リフレッシュできるようになった」といった、ワークライフバランスの向上が期待されています。
✔「何より、時間に追われる焦りが減り、心にゆとりが生まれたことで、子どもたち一人ひとりの小さな変化にも気づけるようになったと感じます」と語る保育士の言葉は、DXがもたらした最も大きな成果の一つかもしれません。
【組織全体の活性化】
✔ チャットワークやウェブ会議の活用は、施設間のコミュニケーションを活性化させ、成功事例や課題の共有を促進 。 組織全体で保育の質を高めていこうという一体感が醸成されています。
✔ 「DXは、単に業務が楽になるだけでなく、私たち自身の働き方や保育への向き合い方を見直す良い機会になりました」と吉村祥枝氏は語ります。
成功のポイント・工夫した点:「やらされ感」ではなく「みんなで創る」。現場主導の改革が生んだ好循環
キッズ・プランニングの働き方DXが成功裏に進んでいる背景には、いくつかの重要なポイントと、きめ細やかな工夫がありました。
【トップの強いコミットメントとビジョンの共有】
臼木淑子代表自らが「保育の質は、職員の働きがいから生まれる」という強い信念を持ち、DX推進の旗振り役となりました。 経営トップが明確なビジョンを示し、改革への強い意志を全職員に伝え続けたことが、取り組みの大きな推進力となりました。
【現場の声を徹底的に吸い上げるボトムアップ型の導入プロセス】
新しいシステムの導入や制度変更にあたっては、一方的なトップダウンではなく、現場の保育士たちの意見を丁寧にヒアリング。 各園の代表者を集めた会議を定期的に開催し、ツールの選定から運用ルールの策定まで、現場の保育士が主体的に関わる形で進められました。
「実際に使うのは私たちなので、使いにくいものは定着しません。だからこそ、みんなで意見を出し合い、納得のいく形を模索しました」と吉村氏は振り返ります。
【丁寧な研修と伴走支援による「使いこなせる」体制づくり】
ICTツールの導入初期には、操作に不慣れな職員も少なくありませんでした。そこで、全職員を対象とした丁寧な研修会を実施。さらに、ICT担当者を配置し、各園を巡回してのフォローアップや、いつでも質問できる相談窓口を設けるなど、きめ細やかなサポート体制を構築しました。 「“導入して終わり”ではなく、“使いこなせるようになるまで”徹底的にサポートする姿勢が、現場の安心感に繋がりました」。
【「まずはやってみよう!」の精神と柔軟な改善サイクル】
最初から完璧を目指すのではなく、「まずは試してみて、課題が見つかれば都度修正していく」というアジャイルなアプローチを取りました 。 現場からのフィードバックを迅速に吸い上げ、運用方法を柔軟に見直すことで、より実態に即した形でDXを浸透させていきました。
【「何のために改革するのか?」目的意識の共有とモチベーション維持】
「DXは手段であって目的ではない。私たちの目的は、子どもたちにより良い保育を提供し、職員が心身ともに健康で、やりがいを持って働ける環境を実現すること」。この目的意識を常に共有し続けることで、変化に対する前向きなエネルギーを生み出し、職員のモチベーションを高く維持しました。
今後の課題、取り組み:地域と共に、未来を育む。持続可能な保育を目指して
ICT活用と変形労働時間制の導入という大きな変革を遂げたキッズ・プランニングですが、その歩みは止まりません。
【さらなるDXの深化と保育の質の向上】
✔ 導入したICTツールをさらに活用し、保育記録の分析や個別最適化された保育計画の立案など、より高度なデータ活用を目指しています。
✔ 職員研修のさらなる充実や、専門性を高めるための資格取得支援などを通じて、保育の質の継続的な向上に取り組みます。
【働きがい」と「働きやすさ」の両立追求】
✔ 変形労働時間制の運用状況を定期的に検証し、職員の意見を反映しながら、より柔軟で働きやすい勤務体系を追求していきます。
✔ メンタルヘルスケアの充実や、キャリアパスの多様化など、職員一人ひとりが長期的に安心して働ける環境づくりを進めます。
【地域社会との連携強化とSDGsへの貢献】
✔ 「創業当初からの理念である『自分を愛し、人を愛し、地域を愛する』ことを大切に、これからも地域との関わりを深めていきたい」と臼木代表は語ります 。 地域清掃や交流イベントといった活動に加え 、インクルーシブ保育の研究なども通じて 、共生社会の実現に貢献していきます。
✔ 環境教育やSDGs達成に向けた取り組みを、子どもたちと共に考え、実践していくことで、未来を担う人材育成にも力を注ぎます。
キッズ・プランニングの挑戦は、保育業界全体の働き方改革をリードし、子どもたちの明るい未来を創造していくための、大きな一歩となることでしょう。
関連情報・ナビゲーション
テレワーク実践事例サイトはこちら
お問い合わせ
日本テレワーク協会 窓口 guide@japan-telework.or.jp (お手数ですが、@を半角に替えてください)